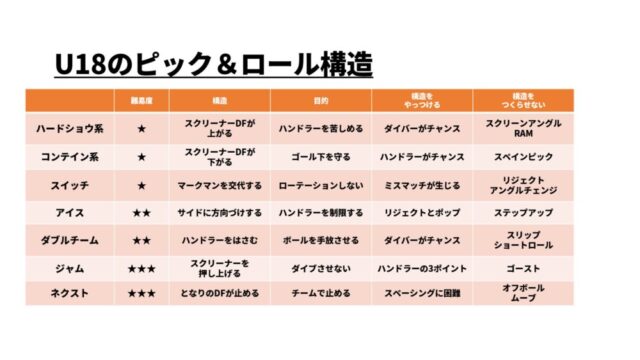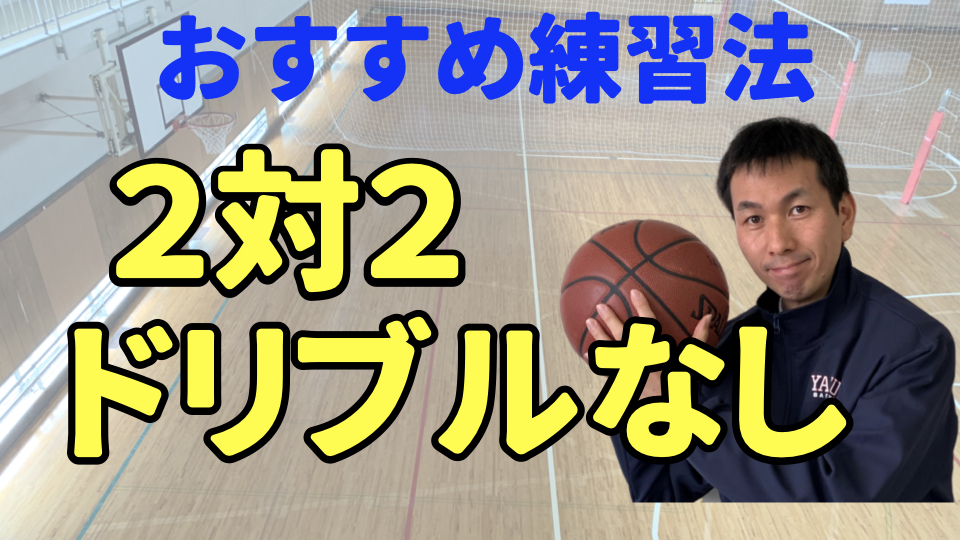こんにちは、三原です。
この記事では「ボックス」というセットオフェンスをわかりやすく紹介します。
スクリーンプレイをうまく使いたい
少し変わったオフェンス戦術をやってみたい
そんな考えのあなたに役立つ記事です。
動画でわかりやすく解説したYouTubeもあわせてどうぞ!
音声だけ聞き流しても学べるように、工夫して作ってあります。
ちなみに、セットオフェンスの全体像については、こちらの記事をぜひどうぞ!
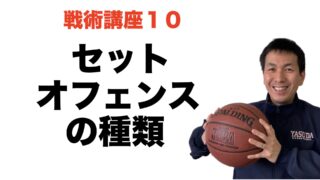
ボックスセットの特徴は「せまさ」
ボックスセットとは、このようにインサイドに4人立つオフェンスです。
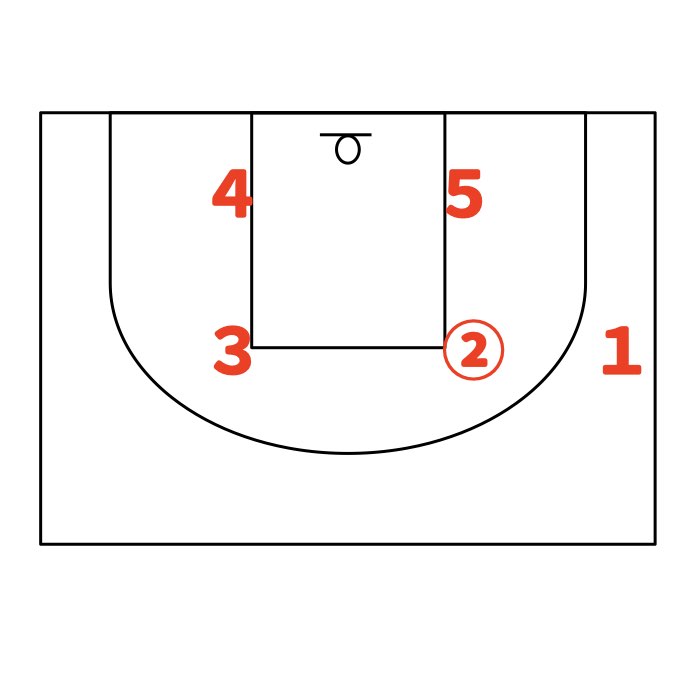
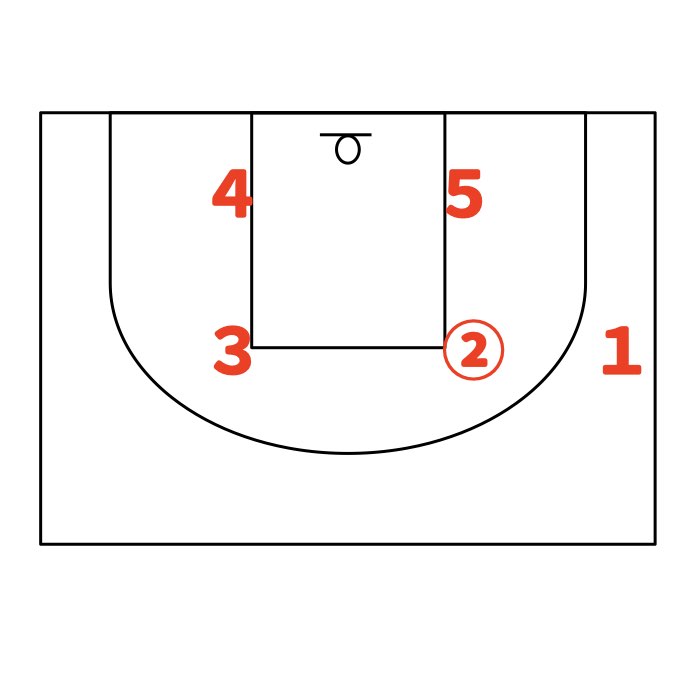
4人も中に立てば、もちろんスペースはせまくなります。
ふつう、バスケットボールのオフェンスはスペースが広い方がうまくいきやすいものです。
なので、せまいということはデメリットになるはずです。
しかし、ボックスセットはあえてせまくするところが魅力です。
というのも、オフェンスがせまくなれば、当然ですがディフェンスもせまくなる。
つまり、ディフェンスにとっては逃げ道がなくなるんです。
あえてせまくすることで、スクリーンプレイがかかりすくなる。それがボックスセットの特徴です。
なので、ボックスセットのプレイは、スクリーンを連続でかけることが多くなります。
この記事では、代表的なプレイを2つ紹介しましょう。
- フレックス
- ジッパー
この2つです。
具体例①フレックス
フレックスは、世界で最も有名なマンツーマンオフェンスです。
まず、このようにボックスセットに立ちます。
- ボールのあるサイドに3人
- ボールのないサイドに2人
このポジションが基本形です。
そして、オフボールのサイドから動き出します。
3が4にダウンスクリーンです。
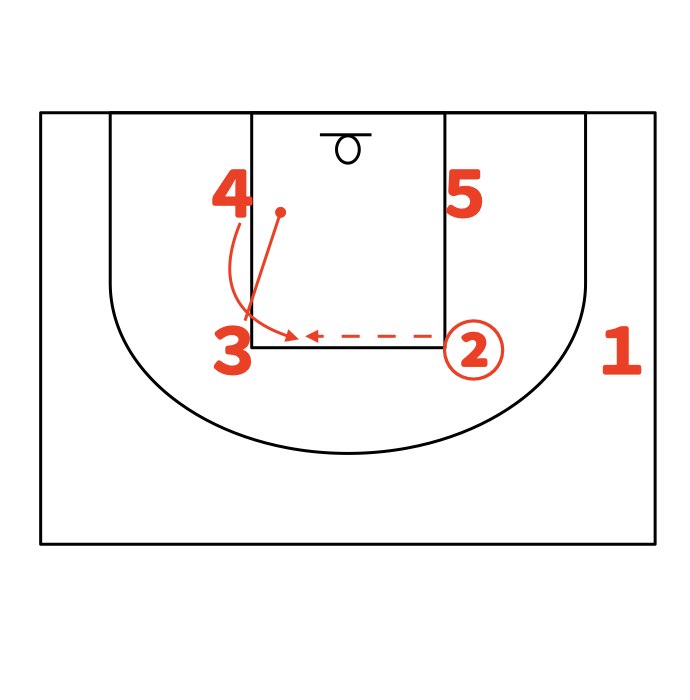
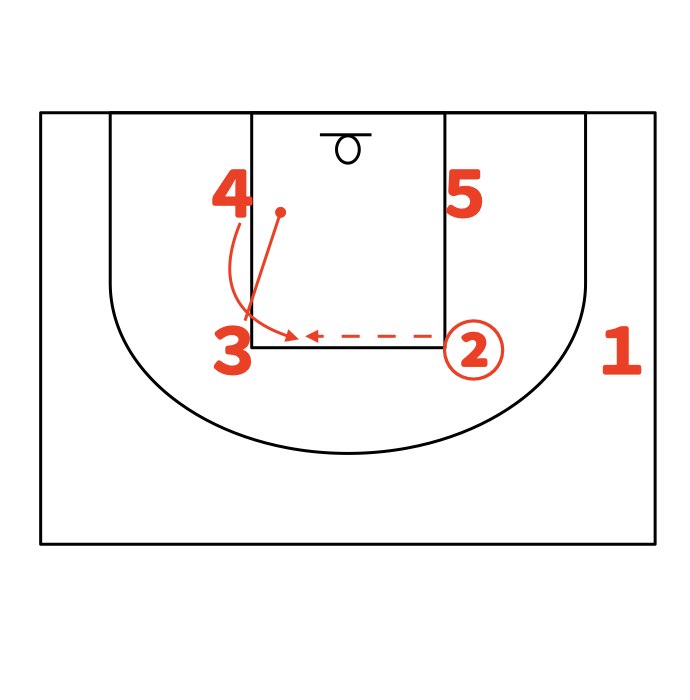
スクリーンをかけたら、3は外に広がりましょう。
そして、その空いたスペースに、5のスクリーンを使って1が飛び込みます。
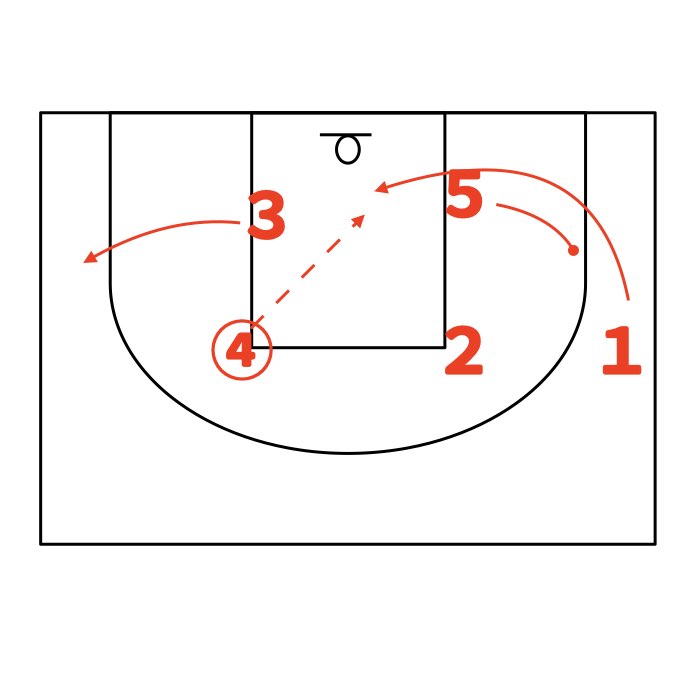
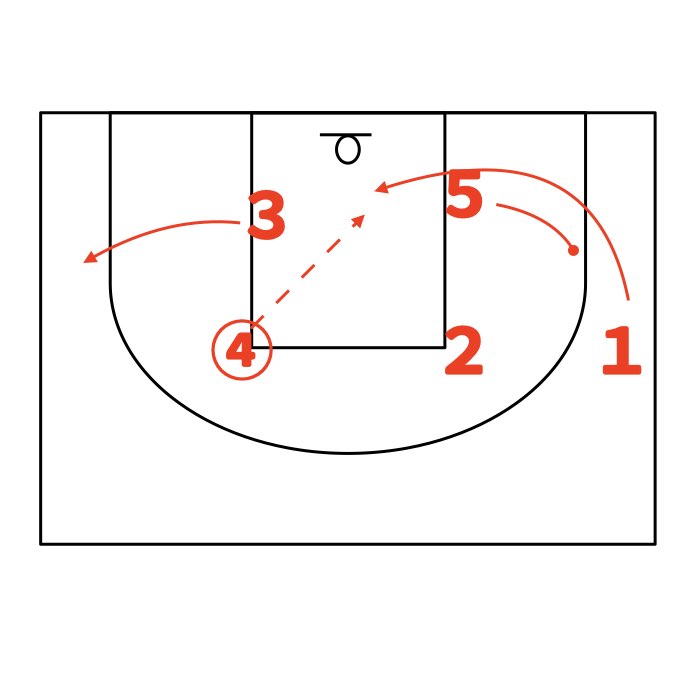
さらに、2が5にダウンスクリーンです。


このように
- ダウンスクリーン
- 広がる
- 逆サイドでバックスクリーン
- ダウンスクリーン
- 広がる
- 逆サイドでバックスクリーン
- ・・・・・・・
こういうループをずっと続けるのが、フレックスオフェンスです。
- ドリブルを使わない
- パスをどんどん回す
- スクリーンが連続でとても守りにくい
- ポジションにこだわない
こういう多くのメリットがあるので、昔から今でも世界中で使われているのがフレックスです。
今回は概要だけお伝えしましたが、より詳しくフレックスを知りたい方は、こちらの記事もお読みください。
具体例②ジッパー
2つめの具体例は「ジッパー」です。
ジッパーとは、カバンや上着についている「チャック」のこと。
チャックを上下させて、開け閉めするような動きのスクリーンプレーを言います。
- 1がドリブルで45度まで下りる
- 5が2にダウンスクリーン
- 2が真上に上がってパスをもらう
このとき、5と2が「ジッパー」のような動きってわけです。
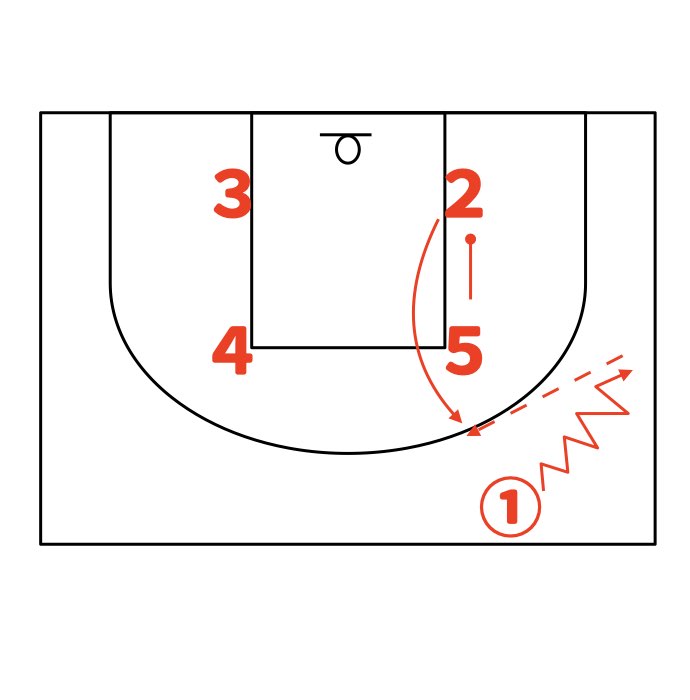
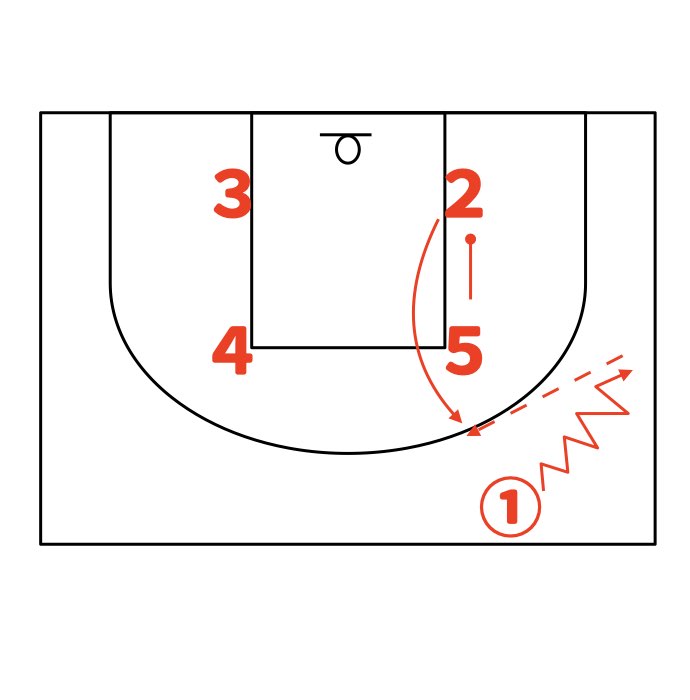
ジッパーのメリットは、ガードポジションでボールをもらったときに、ディフェンスを後追いの状況にできること。
ふつう、トップのガードポジションって、一番きつく守られるところですからね。
それがもらった瞬間から、オフェンス有利な状況を作れるわけです。
このジッパーに続くプレイとしてはいろいろ考えられますが、よくあるパターンは2に4がピック&ロールを仕掛けるプレイでしょう。
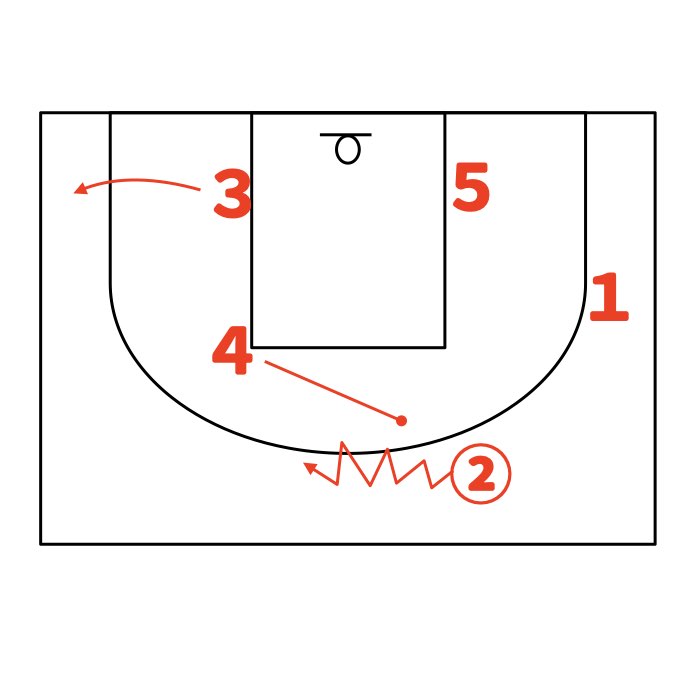
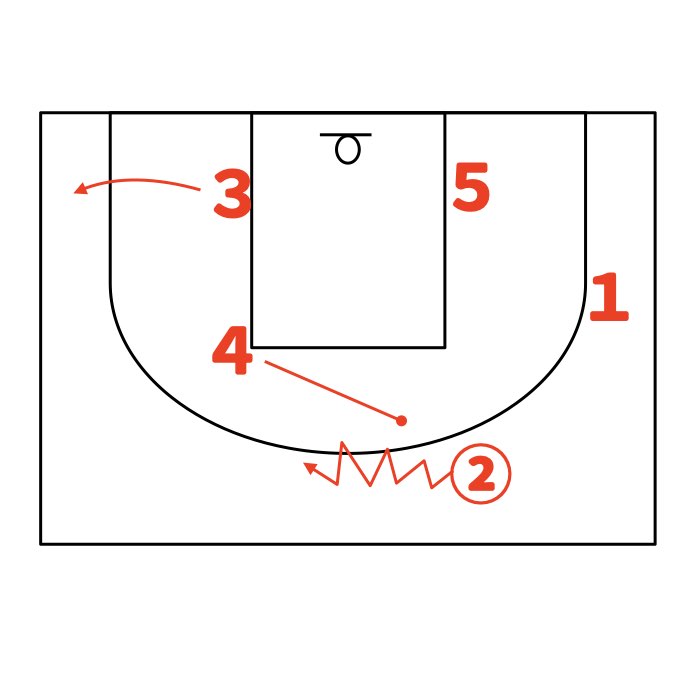
2のディフェンスからすると、時間差で別のスクリーンが襲いかかってくるので、すごく守りにくいです。
いろいろ使い道があるジッパースクリーン。ぜひ試してみてください。
ボックスのデメリット
デメリットはなんといっても、せまいことです。
なので、アウトサイドからドライブはまったくできません。
また、制限区域内でのプレイが多いので、身長差も影響しやすく、背が低いチームにはあまり向かないです。
フレックスをやる場合は、コートいっぱいに広がって行ったり、フリースローラインよりも全員が上に上がって「ハイフレックス」をやることもできます。
しかし、原形のボックスセットはせまいプレイです。
ガード主体で、スピードが持ち味のチームがやると、あまり効果がないかもしれません。
まとめ
- ボックスセットはせまいことが特徴
- せまいからスクリーンがかかりやすい
- 代表的なプレイは「フレックス」
- 縦と横のスクリーンを連続して行う
- もうひとつは「ジッパー」
- チャックの開け閉めのように動くスクリーン
- ガードで有利なプレイが作りやすい
- ボックスのせまさはデメリットにもなる
- 外からのドライブは一切なくなる
- スピード重視の小さいチームには向かないかも
というお話です。
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。