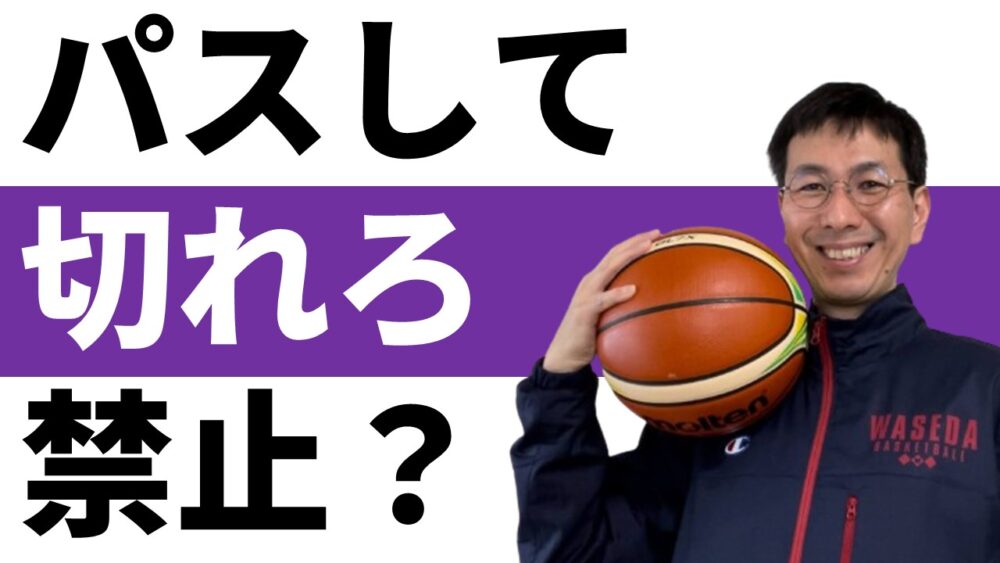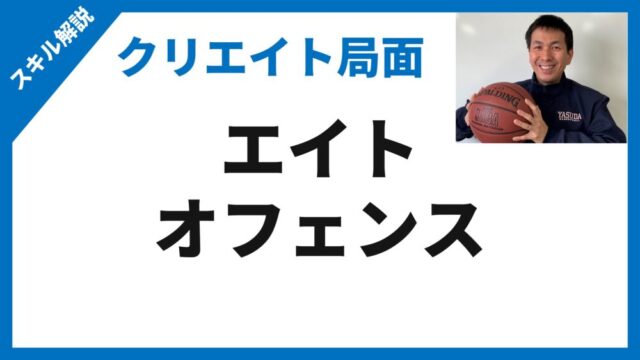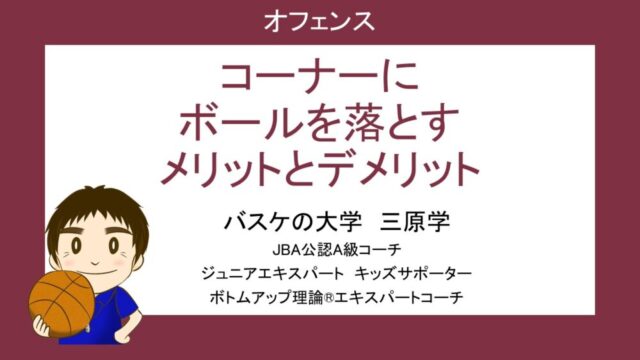「パスして切れろ」は選手を下手にする?
こんにちは、三原です。今日もありがとうございます。
今回のテーマはちょっと挑発的です。
「パスして走れ」――指導の現場でよく聞く言葉ですよね。私も言ってきました。
でも、実はこれを“禁止”した方がいいんじゃないか?そんな話をしたいと思います。
きっかけは海外の動画
ある日、YouTubeで「Transforming Basketball」という海外のチャンネルを見つけました。
サムネイルには大きく「パスしてカットは禁止!」と書いてあって、思わずクリック。
内容はこうでした。
-
小学生やU12年代でよくある「パスしたらカット」の5アウトオフェンス。
-
これはコーチの目には動いているように見えて気持ちがいい。
-
でも実は、選手は形だけを覚えているだけ。
-
だから一番大事な「ディフェンスとの駆け引き」「状況判断」が育たない。
つまり「子供たちを下手にする」というのです。
私はこれを見て「うん、その通りだな」と思いました。
ただし同時に「動くことは大切」だとも思うんです。
オフェンスの本質はシンプル
私の考えはシンプルです。フォーメーションは何でもいい。むしろ、なくてもいい。
大切なのはこの3つだけです。
-
まずリングにアタックする
-
ディフェンスが寄ってきて1対2になる
-
そこでパスを出す
この流れさえあれば、どんな戦術でも成立します。
逆に、この原則がなければ全部ただの「形」になってしまうんです。
だから「パスして切れろ」を徹底すると、選手が最初から“パス優先”になってしまう。
結果、攻める姿勢がなくなり、オフェンスが弱くなるんです。
ボールを持ったら優先順位を間違えるな
ボールを持った時にできることは3つ。
-
シュート
-
ドリブル
-
パス
この順番がとても大事です。
-
まずシュートを狙う
-
打てなければドリブルで攻める
-
それでヘルプが来たらパス
これが正しい流れです。
ところが「パスして切れろ」ばかり強調すると、ボールを持った瞬間に“まずパス”を探してしまう。
これでは本来のオフェンス力が育ちません。
動きには必ず「目的」が必要
じゃあ「動くな」なのか?というと、もちろん違います。
動くことは大事。でも、そこには“目的”が必要です。
例えば――
-
ボールをもらいやすくするためのカッティング
-
味方が1対2で苦しんでいるときの合わせ
-
ディフェンスをずらすためのスクリーン
こういう動きは必要不可欠です。
逆に、ただ「言われたから動いている」だけのカットは不要。
むしろ邪魔になるとさえ思います。
だから私は選手にこう聞きます。
「今の動きは何のため?」
答えられないなら、その動きはしない方がいい。
まとめ
「パスして切れろ」――目的がなければ、選手を下手にします。
-
ボールを持った瞬間はまずシュートを狙う
-
それができなければドリブル
-
最後にパス
この順番を徹底することが、オフェンス上達の近道です。
一方で「意味のある動き」は絶対に必要。
チャンスを作るため、味方を助けるため。そこに目的があるなら、どんどん動いた方がいい。
ぜひ今日の練習で、選手の動きを観察してみてください。
「今の動きは何のため?」と問いかけてみる。
それだけでチームのオフェンスはガラッと変わります。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。