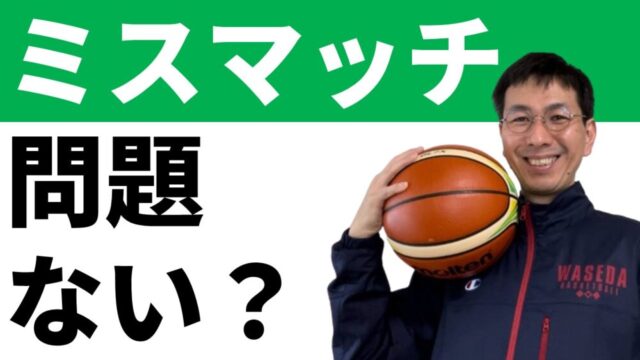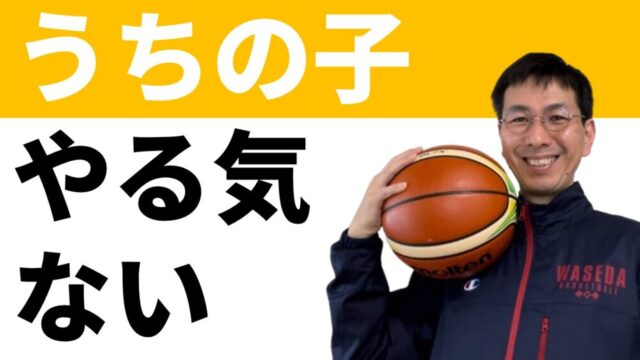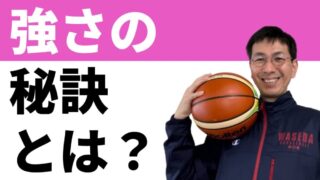【シザースカット】3人でできる基本オフェンス!わかりやすく解説します
こんにちは、三原です。
今日は、オフェンスの基本中の基本「シザースカット」についてお話しします。
きっかけは、YouTubeのコメント欄にいただいたご質問でした。
こんばんは。自分は社会人バスケをしているものです。
中学生までしかバスケをしていなかったためか、細かな戦術がよく分かりません。
「シザースカット」のはっきりした動きが知りたいです。
この質問を読んで、「あれ?そういえばちゃんと説明してなかったな」と気づきました。
シザースカットはとてもシンプルで効果的な戦術です。
今回は、3人でできるシザースカットを中心に、
基本と応用、それから実戦での活かし方まで、わかりやすく解説します
シザースカットって何?
「シザース(scissors)」は、英語で“ハサミ”という意味。
つまり、交差するカットの動きをハサミにたとえて、そう呼ばれているんです。
3人の登場人物がいます。
-
トップ(1番)
-
ウイング(2番)
-
ハイポスト(3番)
1番が3番にパスをしたら、その1番が最初にカット。
そして、2番が交差してカットします。
この「交差」=「ハサミの動き」だからシザースカット。
ポイントは、最初にパスをした人が最初にカットすること。
これを“トリガー(引き金)”にして、プレーが自然に始まります。
一瞬で4人(オフェンス2+ディフェンス2)がごちゃっと集まるから、
ディフェンスは混乱しやすく、パスも通りやすい。
シンプルだけど、すごく有効な動きなんです。
応用パターンは2つでOK
基本を覚えたら、応用も試してみましょう。
おすすめのパターンはこの2つです。
▶ バックドアカットと組み合わせる
1番がパスした直後に、逆側から裏にスッと抜ける(バックカット)。
ディフェンスが前に出ていれば、そのままレイアップチャンス。
もし通らなくても、そのままゴール下でスクリーン役になることで、
2番のカットをサポートできます。
▶ スプリットアクションと組み合わせる
1番が3番(ローポスト)にパス。
そのあと1番がディフェンスの横で一瞬止まってスクリーン。
そこを2番が利用して3Pを狙う。
2番がフェイクして逆にバックドアへ抜けてもOK。
ウォリアーズがよくやる形です。
実戦では3対3で練習→自然に5対5へ
「これ、どうやってチーム練習に取り入れればいいの?」
と迷った方も大丈夫。
答えはとてもシンプルです。
👉 まずは3対3で練習して、自然に5対5に応用すること。
ボールサイドで3人がシザースカット。
残りの2人は、ヘルプサイドにスペーシングをとるだけ。
これだけで、実戦でも使える5人の動きになります。
がっちりしたフォーメーションにこだわらなくてOK。
まずはシンプルな3対3で連携を身につけましょう。
最後に今日のまとめです。
-
シザースカットは「パス → カット → 交差」のシンプルな動き
-
パスした人が最初にカットするのが基本
-
バックドアやスプリットアクションと相性抜群
-
3対3で練習すれば、自然に5対5へつながる!
100年たっても使われるプレーには、理由があります。
今どきの華やかな戦術に目移りしがちですが、
「シンプルで強い動き」を繰り返し練習することが、いちばんの近道だと思っています。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。