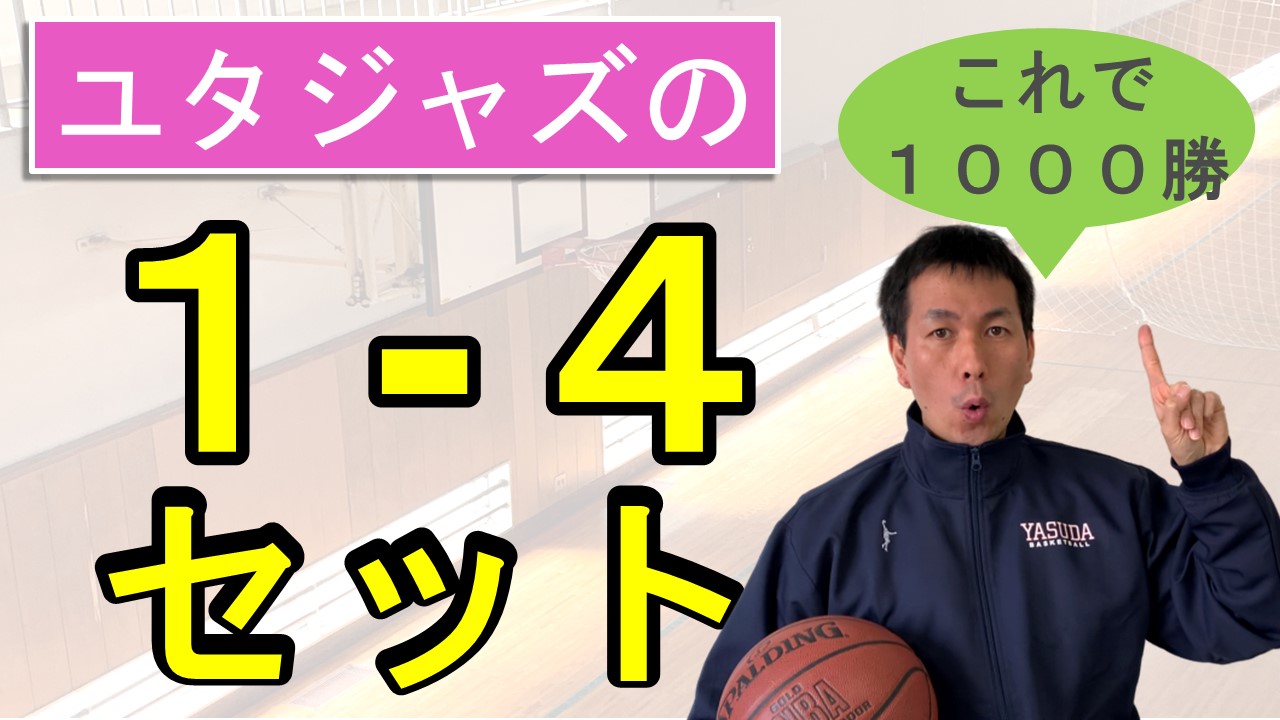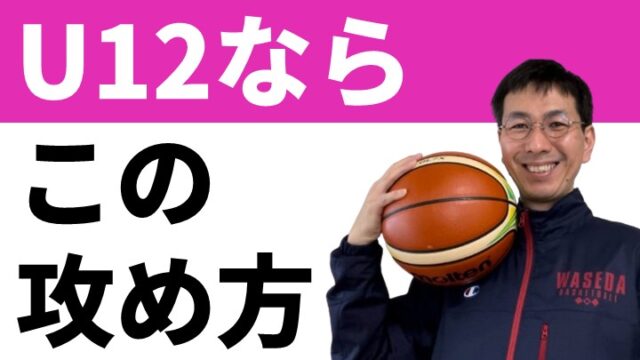ゴール下でシュートができる合わせ方
~ショートコーナーの使い方を考える~
こんにちは、三原です。
いつもありがとうございます。
今回は「ゴール下でシュートができる合わせ方」というテーマでお話しします。
特に「ショートコーナー」という場所をどう活かすかに焦点をあてます。
前回の動画でこのショートコーナーの話をしたところ、
「ミニバスでも使えそうです」「すぐ練習で試してみました」と、たくさんの反応をいただきました。ありがとうございます。
なので今日はその続きです。
ショートコーナーにボールを入れてから、どんな合わせをすれば、高確率でゴール下のシュートになるのか?
その考え方と具体例をお届けします。
なぜショートコーナーなのか?
まずはおさらいです。
ショートコーナーというのは、
ペイントエリアのすぐ外、3Pラインのすぐ内側、エンドライン沿いのスペースです。
この位置にボールを入れると、ディフェンスが困ります。
なぜかというと、「ボール」と「自分のマークマン」の両方を同時に見るのが難しくなるからです。
トップやウイングにボールがあると、守る側は視野に両方入れることができる。
でも、ショートコーナーにあると、そうはいかない。どっちかしか見えないんです。
これが何を意味するかというと、
合わせのカッティングがとても効くということです。
たとえば、ショートコーナーにパスを入れた直後にギブ&ゴー(パスして走る)をすると、
驚くほど簡単にレイアップのチャンスが生まれます。
理由はシンプルで、ディフェンスが「見えてないから」です。
同じプレーでも、ボールの高さで結果が変わる
ここで、ちょっとした発見を共有します。
3対3のプレーで、トップからアウェイのスクリーン→カールカットという流れがありますよね。
これ、トップでやると、シュートチャンスはミドルジャンパーです。
でも、まったく同じ動きをショートコーナーの位置でやると、レイアップになります。
これ、すごくないですか?
ボールの位置がちょっと下がるだけで、同じプレーでもゴールに近づける。
わたしはここに、オフェンス戦術の「本質」があると思っています。
よく「チームでプレーしよう」って言いますよね。
それってつまり、「みんなでボールをゴール下まで運ぼう」ってことだと、わたしは思うんです。
高さのあるジャンパーより、リングに近いレイアップの方が入る。
当たり前なんですが、それを意識的に実行するのは難しい。だからこそ、仕組みを作る。
その一つが、ショートコーナーを使うオフェンスなんですね。
背が低くてもできる、ゴール下のバスケット
具体例をひとつご紹介します。
5アウトの形から、ウイングの選手がショートコーナーへスライド。
そこにボールを入れたら、パスをした選手がすぐカット。
このカットにディフェンスがついてこられなければ、シンプルなリターンパスでレイアップです。
もしついてこられても大丈夫。
ショートコーナーにスペースができているので、その選手がミドルにドライブして1対1。
さらにそこから、カットした選手が逆サイドにスクリーンをかけに行く。
5番の選手がコーナーから上がってきて、ショートコーナーの選手とドリブルハンドオフ。
この連携から、4番の選手がそのまま1対1に行ってもいいし、再びハンドオフしてもいい。
何にせよ、リングの近くでシュートを打つ流れが作れるんです。
これ、サイズのある選手じゃなくてもできる。
つまり、背が低くても2点を確実に取りにいける方法です。
大きなポストプレーが難しいチームこそ、ショートコーナーを活用すべきです。
わたしはそう思っています。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。