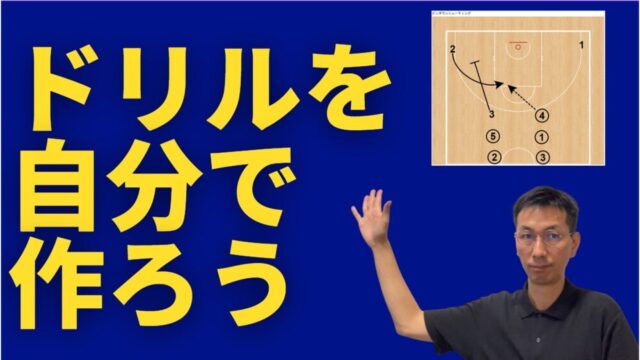大学運動部の不祥事はなぜ起こるのか?
こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。
今日は少し真面目なテーマ、「大学運動部の不祥事はなぜ多いのか?」について、わたしなりの考察をお話しします。
不祥事が続く現状と、考えるべきこと
最近の大学スポーツでは、不祥事が相次いで起きているのが現実です。具体的な大学名は挙げませんが、さまざまな部活動で、さまざまなタイプの不祥事が起きています。わたしも大学で指導にあたる立場として、この問題には非常に敏感です。
「なぜこうなるのか?」「自分にできることはないか?」という問いに向き合うべく、今回はわたし自身の考えを整理してみたいと思います。
わたしの結論:「成長する組織」と「卒業生の支え」
もちろん、絶対の正解はありません。ただ、あえて言うなら、わたしが考える理想はこうです。
「成長する組織を卒業生がバックアップする」
この形が、大学運動部をより健全に、より良い方向に導く一つの答えではないかと思っています。
勝利至上主義のひずみ──中間層の苦しみ
大学スポーツは、学生スポーツの中でも最高峰です。だからこそ、どうしても「勝つこと」に価値が置かれます。生活面や人間的な成長よりも、結果重視。これが当然のようになっているのが現実です。
その結果、選手やスタッフに大きなプレッシャーがかかります。とくにレギュラー選手には精神的・肉体的な負荷が重くのしかかります。連戦や海外遠征など、タフな環境で戦うことも少なくありません。
問題はその影響が「中間層の選手」に出やすいことです。上位の選手は注目され、初心者は学びが多い。でも、中間の選手は、どちらにも属せず、成長も見えにくい。その苦しさからくるストレスが、何かの形で外に出てしまう。これが不祥事の背景にあると、わたしは見ています。
学生主体と放任
次に「学生主体」について。
大学の運動部は、教職員やボランティアの指導者によって支えられているケースが多く、どうしても“目が行き届かない”構造になりがちです。
「学生主体でやらせる」という方針もよく聞きますが、これは誤解を生む危険があります。学生主体と放任は違います。指導者がビジョンを持って任せるのが学生主体であり、ただ「任せっきり」では何も育ちません。
わたしの経験では、一人の指導者が本気で目を配れるのは10人程度。それ以上になると、目が届かなくなります。だから、30人いれば3人、50人いれば5人の大人が必要。それが最低限のラインです。
OBOGの力こそがカギ
ですが、大学が部活動のために何人も人員を割くのは現実的ではありません。そうなったときに頼りになるのが、卒業生(OBOG)の力です。
現役時代にチームを大切に思っていたOBOGが、今度は支える側に回る。定期的に練習に顔を出し、後輩の話を聞き、悩みを受け止める。そういう姿勢が、いまの大学運動部には求められています。
大会の日にだけ現れるのではなく、普段の練習場所に気軽に顔を出せる。そういう卒業生が多いチームほど、健全で安心感のあるチームになります。わたしはそう信じています。
まとめ:「育てる」文化が必要
大学運動部の不祥事は、個人の問題ではなく、組織の構造に原因があります。
-
勝利至上主義による中間層の苦しみ
-
指導者不足による目の届かない現場
-
放任に陥る“学生主体”の誤解
-
支え合いが不足するチーム体制
こうした課題に対して、「成長する組織を、卒業生が支える」という考え方が、現実的な解決の第一歩になるとわたしは考えています。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。