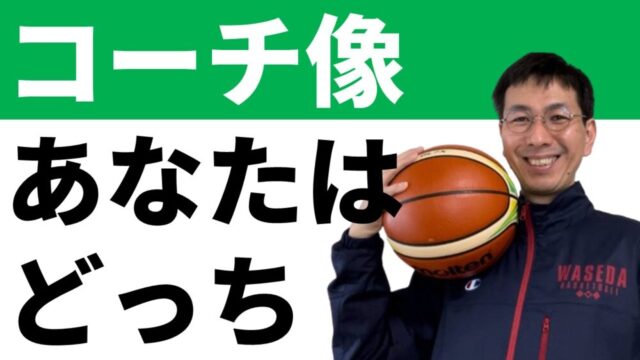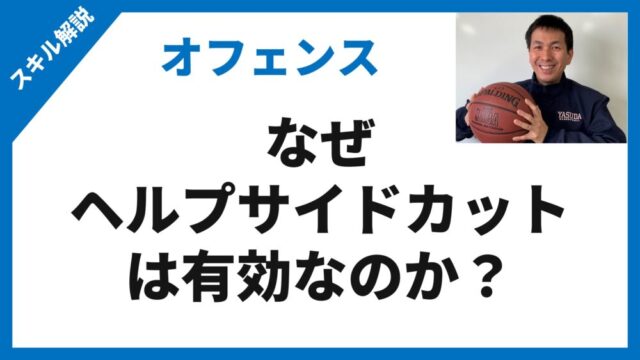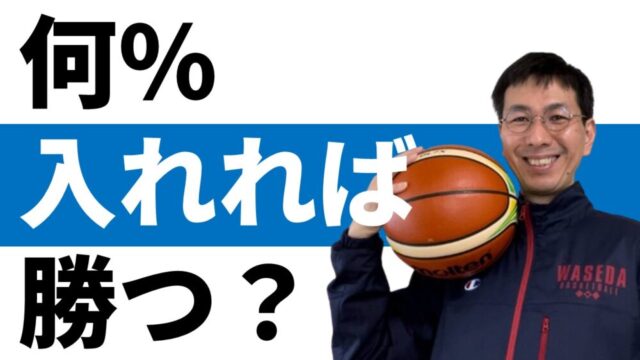右手を生かせば、オフェンスが変わる
こんにちは、三原です。
今日のテーマは「右手をもっと使おう!」というお話です。
あんまり他で聞かない話かもしれませんが、これ、けっこう大事な視点です。
練習では「左右バランスよく」が基本。右も左も同じようにドリブルして、同じようにレイアップする。もちろんそれは大切。でも、実際の試合になったら、得意なほうを使った方がよくないですか?
そう思ったので、今日はちょっとユニークな視点で、オフェンス戦術を深掘りしてみます。
右利きガードなら、左レーンから始めよう
まず、速攻の場面から。
速攻といえば、両サイドのウイングが走って、センターはまっすぐリムラン。ガードがボールを持って上がってくる、という形が基本ですよね。
このとき、ガードが右サイドを運ぶか、左サイドを運ぶか。これ、どっちでもいいように思うかもしれません。でも、右利きの選手なら、実は「左レーンから右手で攻める」方が、すごくやりやすいんです。
たとえば、ドラッグスクリーンのプレー。トレーラーの4番がスクリーンにきて、ガードがドリブルを引っ張っていく。これ、右サイドから始めると左手ドリブルになります。右利き選手にはちょっと負担ですよね。
でも、最初から左レーンを運んでおいて、そこから右手で中央にドライブできるように設計しておけば、ドリブルもパスも、右手でやりやすいんです。
この右手でのフックパス、逆サイドのシューターに出すときも精度が高くなります。逆に左手でフックパスを投げるのは、かなり難しい。
だから私は、可能な限り「左サイドから右手で攻める」設計をするようにしています。
ポストプレーも右手中心で考える
ポストプレーでも、この「右手中心」の考え方は活きます。
たとえば、左ウイングの選手(3番)がポストにボールを入れる。このとき、パスは左手になるかもしれませんが、その後が大事。
3番がそのままカットして、リターンパスをもらうとき、ポスト(5番)は右手でパスを出せます。そして3番も、右手でそのままレイアップに行ける。
これが逆サイドだと、パスもレイアップも左手になってしまって、少し難易度が上がりますよね。
また、もしリターンパスが通らなくても、5番がボールを持って1対1に行くとき、右側にドライブして右手でフィニッシュしやすい。さらに、外の2番や1番にキックアウトするときも、右手でパスが出せる。
こういう風に、「右手でできることが多い」ポジションに設計しておくと、選手にとってはプレーしやすいし、ミスも減ります。
練習はバランス、試合は得意を活かす
もちろん、練習では左右どちらでもやります。
右手だけでバスケはできませんからね。ドリブル、パス、レイアップ、すべて左右両方できるようにすることは、とても大切です。
でも、実際の試合では「強い方を使おうよ」と思うんです。利き手の右を活かせば、それだけでパスやシュートの精度が上がる。つまり、得点につながる確率が高くなるわけです。
だから、戦術設計のときに「どのサイドから攻めるか?」を、選手の利き手に合わせて設計する。これだけで、オフェンスがすごくスムーズになります。
おわりに
今日の話、まとめるとこんな感じです。
-
右利きの選手には、左レーンから右手で攻める設計がオススメ
-
ドラッグスクリーンやポストプレーでも、右手が使いやすい設計にする
-
練習では左右バランスよく、試合では得意な方を最大限に使う
右手を活かせば、オフェンスがもっと生きる。これはちょっとしたアイデアですが、試合の流れや選手のプレーに大きな影響を与えます。
よかったら、あなたのチームでも取り入れてみてください。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。