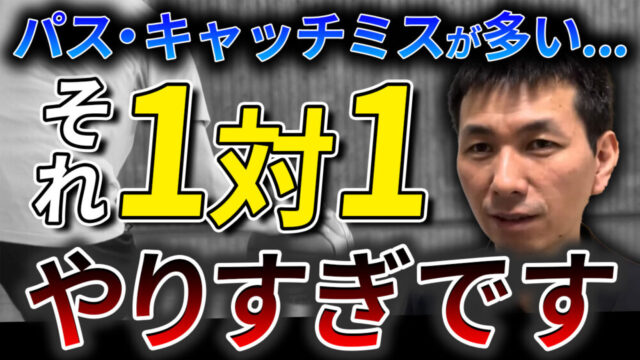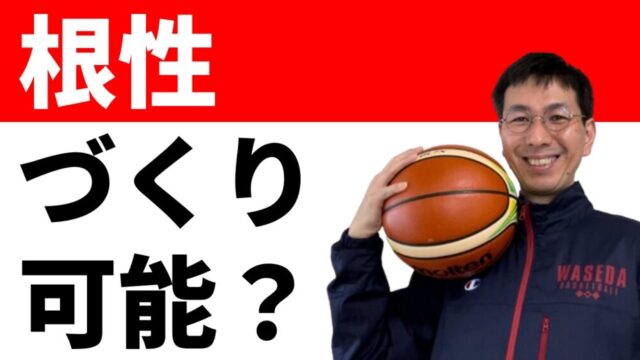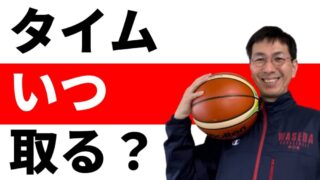なぜJBAはマンツーマンを推進するのか?
こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。
今日は、最近あらためてJBA(日本バスケットボール協会)が出した「マンツーマン推進」の資料について、わたしの考えをお話しします。
http://www.japanbasketball.jp/players_development
コーチのあなたも、きっとこんな疑問を持ったことがあるでしょう。
「なんでマンツーマンにこだわるんだろう?」
試合で勝つためなら、ゾーンディフェンスを使った方が効率的。
大きい選手をゴール下に立たせて、中を固めて、外は打たせておけばいい。
これで簡単に勝てる試合、ありますよね。
でも、それで本当に選手たちは成長するんでしょうか?
今日は、そんなお話です。
マンツーマンを推進する理由
まず、基本的な背景を知っておきましょう。
2015年から、JBAは15歳以下のカテゴリーで実質的にゾーンを禁止しました。
理由ははっきりしています。
ゾーンでは個人技能が身につかないから。
2015年以前の全国大会では、小学生も中学生も、強いチームほどゾーンを多用していました。
もちろん当時はルール違反じゃありません。
戦術としては正解ですし、勝つための近道でした。
ただ、そればかりやっていると、選手たちが「1対1で抜く力」「守る力」を学べない。
結局、上のカテゴリーに行った時に通用しなくなる。
だから、JBAは決断したんです。
「勝つため」よりも、「育てるため」を優先しよう、と。
マンツーマンの基本
今回の資料で特に面白かったのは、ゾーンとマンツーマンの境界線が具体的に書かれていたことです。
ざっくり言うと、NG例は3つあります。
① ゴール下に立ちっぱなし
大きい選手がゴール下にずっと居座っている守り方。
これ、たしかに試合では役に立ちますが、選手本人は上手くなりません。
ボールが外に出たら、ついて出ていく努力をさせましょう。
② マークマンを見失う
ボールに夢中になって、マークしている相手を放置してしまう。
これもマンツーマンではありません。
ボールも人も見る、視野のトレーニングが必要です。
③ 専門のトラップ要員
誰かが常にダブルチームに飛び出してばかりいる。
これも短期的には効果的ですが、守るべき相手を守る力が育ちません。
指導者の「倫理」が試される
資料には、こんな言葉がありました。
「マンツーマン推進は、指導者の倫理が問われるものです。」
正直、ドキッとしました。
ルール違反さえしていなければいい、ではないんです。
目の前の試合で勝つために、大きい選手をゴール下に貼りつけて、ゾーンのような守り方をさせる。
これが、はたしてその子のためになるのか?
指導者として、その判断が試されているわけです。
マンツーマンが強い理由
最後に、わたしの持論もお伝えしておきます。
はっきり言って、マンツーマンディフェンスは最強の守り方です。
NBAでも、国際大会でも、最終的にマンツーマンの強さが勝負を決めます。
ゾーンや変則ディフェンスは「一時的なごまかし」に過ぎません。
しっかりとポジション、視野、声を鍛えて、ガチガチのマンツーマンで守れるチームは強いです。
これは間違いありません。
マンツーマンで育てることで、勝利も必ずついてきます。
「育成か勝利か」ではなく、「育成こそが勝利につながる」ということですね。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。