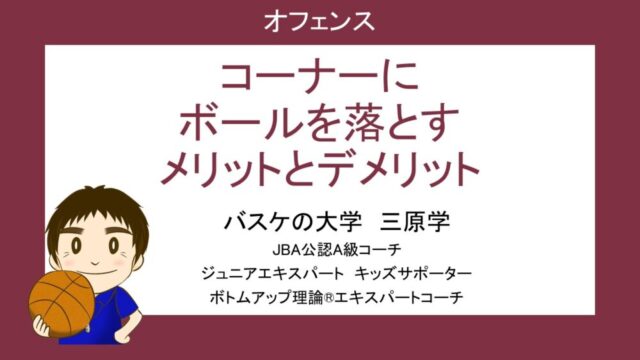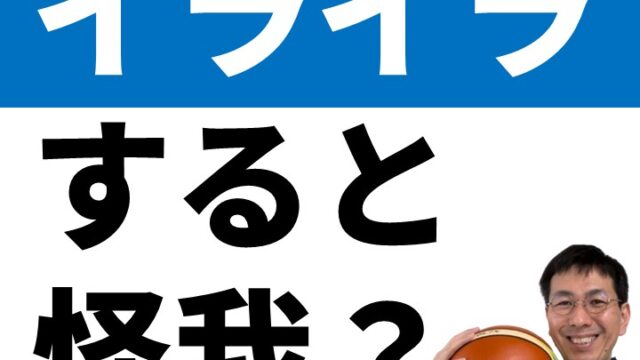パスミスを減らすには?判断力を鍛える2対1・3対2練習法
こんにちは、三原です。
今日も「バスケの大学」にお越しいただき、ありがとうございます。
今回は「パスミスを減らすにはどうすればいいですか?」という質問にお答えしていきます。
特にアンダー10、10歳以下の子どもたちに向けたアドバイスです。
試合で多いパスミス。その原因は?
試合を見ていて「なんでそこにパス出すの?」というシーン、ありますよね。
ディフェンスが目の前にいるのに、なぜかその方向にパスを出してしまってカットされる。
ミスになって、速攻をくらう。
これは「判断ミス」なんです。
つまり、パスが下手なんじゃなくて、判断を間違えているということ。
にもかかわらず、どうしてもパスミスを減らしたいと思うと、
「じゃあチェストパスを練習しよう」とか「オーバーヘッドの精度を上げよう」とか、
実行ばかりに注目してしまうんですね。
でも、大事なのはその前の認知と判断。
バスケットでもっとも大切なステップは、
「認知 → 判断 → 実行」なんです。
これは車の運転と一緒です。
信号が赤だと気づく(認知)、止まろうと決める(判断)、ブレーキを踏む(実行)。
運転免許教習でも教わりますよね。
ミスの原因は「実行」ではない
バスケットも同じです。
「ディフェンスが前にいるな」と気づき(認知)、
「だったらパスをやめよう」(判断)、
「ドリブルで逃げよう」(実行)。
この流れが大事なんですが、
現場での練習はどうしても「パスの技術=実行」に偏りがち。
でも、試合で起きているのは判断ミス。
だったら、練習も判断力を鍛えるべきなんです。
そこで、わたしがいつもお勧めしているのが「2対1」「3対2」のアウトナンバー練習です。
アウトナンバー練習のすすめ
例えば2対2だと、お互いに守りあって攻めあって…で難易度が高い。
でも、2対1にしてあげると、オフェンスに余裕ができて、判断に集中できるんですね。
つまり「実行」の負荷を減らして、「認知」と「判断」に集中できるようにしてあげる。
この構造がとても大事です。
2対1の練習では、味方と2人でボールを持って、真ん中に1人ディフェンス。
このときに見るべきは「味方」でも「リング」でもなく、「ディフェンス」です。
-
ディフェンスが自分を守っていたら、パス。
-
ディフェンスが味方に行ったら、自分でシュート。
たったこれだけのシンプルなルールで、判断の練習になります。
ドリブルのコツ:内側の手でつく
2対1練習をする際に、ひとつだけ小さなコツを。
ドリブルは内側の手でつくといいです。
たとえば右側を攻めるときは、左手でドリブル。
これ、逆に感じるかもしれませんが、内側でドリブルすると片手でスムーズにパスが出せるんですね。
右手でドリブルしてしまうと、いったん止めてからパスをしないといけない。
その一瞬が、相手に読まれます。
ぜひここも工夫してみてください。
3対2では「奥のディフェンス」を見よう
次に、3対2のアウトナンバー練習です。
これは2対1よりも少し複雑になりますが、判断力を養うのにとても効果的です。
ポイントは、「手前のディフェンスではなく、奥のディフェンスを見る」ということ。
トップの選手がボールを持ち、左右に味方がいる状況。
ディフェンスは縦に2人並んでいます。
このとき、パスを出す先を決めるのは、奥のディフェンスがどちらを守っているかによって判断します。
-
奥のディフェンスが右に寄っていたら、左へ。
-
奥のディフェンスが左に寄っていたら、右へ。
こういう視点を持つことで、先読みする力が養われます。
「判断の練習」をしよう
2対1も3対2も、いずれも「実行」ではなく「判断」に集中する練習です。
これが、試合でのパスミスを減らす第一歩になります。
パスミスというのは、「技術のミス」ではなく「判断のミス」。
この考え方をぜひ、チーム全体に浸透させてほしいです。
ミスを許容する「遊び心」も大切に
最後に、ちょっと精神的なお話を。
バスケットというのは、「相手がいるスポーツ」です。
だからこそ、少しぐらいおくれた判断がちょうど良かったりします。
特にオフェンスでは、「真面目すぎるプレー」よりも、少し遊び心のあるプレーの方が、上達につながることがあります。
子どもたちにはぜひ、どんどんチャレンジしてほしい。
そしてそのチャレンジをしやすい環境づくりとして、
「アウトナンバー練習」がとても有効だとわたしは思っています。
2対1、3対2。
簡単なようで奥が深い。
これを毎日5分でも取り入れてみてください。
判断力が変わります。
パスミスが減ります。
あなたのチームの成長に、きっとつながるはずです。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。