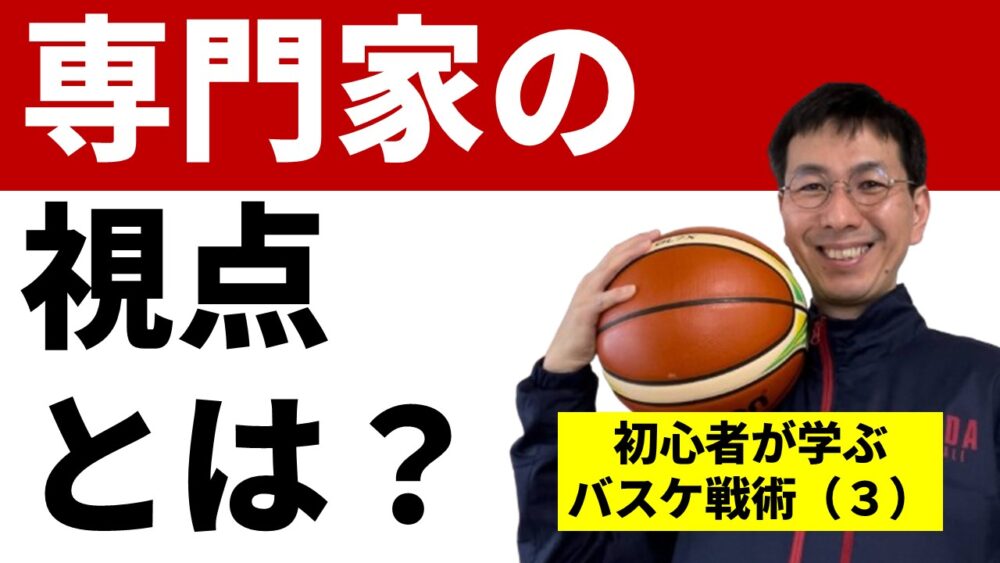バスケ専門家が持つ2つの視点
【まったくの初心者がゼロから学ぶバスケ戦術 第3回】
こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。
今日は「専門家の視点」というテーマでお話をします。
試合を見ているとき、あなたはどこに目を当てていますか?
そして、選手に声をかけるとき、どんな言葉を使っていますか?
実はここが、コーチとしての専門性を分ける大きなポイントなんです。
経験年数よりも大切なこと
「自分は専門家です」と胸を張って言えますか?
私は、専門家かどうかを決めるのは経験年数ではないと思っています。
長くやっていても視点が浅ければ専門家とは言えないし、
逆に若い指導者でもしっかり視点を持っていれば立派な専門家です。
そのカギになるのが、この2つ。
-
アクションに分解できること
-
専門用語を使えること
これがあるかどうかで、指導力はまったく変わります。
1つ目:アクションに分解する力
試合を見ていて、
「なんだかごちゃごちゃしてて分からないな…」
と思った経験はありませんか?
誰がシュートを決めたかは分かる。
でも、その前にどんな動きがあったのか説明できない。
これが初心者の視点です。
一方で、専門家はプレーを「アクション」に分けて見ます。
アクションとは、2人や3人のまとまった動きに名前をつけたもの。
たとえば——
-
ダブルドラッグ
-
スタガースクリーン
-
カール&ポップアウト
-
イグジットスクリーン
こういう風に分解して捉えると、
さっきまでの「ごちゃごちゃ」が一気に整理されます。
「あ、今のはダブルドラッグだな」
「ここはスタガーでシューターを上げたな」
こんな風に見えるようになると、もう専門家の目ですよね。
おすすめは、試合を見ながら紙とペンでアクションを書き出すこと。
これは本当に力がつきます。
2つ目:専門用語を使う力
「小学生に難しい言葉を教える必要はない」
そう思う方もいます。
でも私は、専門用語は積極的に使った方がいい と考えています。
理由はシンプルで、一言で済むから です。
例えば「プルアップ」。
「ドリブルして急に止まって素早くシュート」と長く説明しなくても、
「プルアップ狙おう」で済みます。
これは選手同士の会話でも同じです。
「そこフレアに動いて」
「パックラインで守ろう」
こう言えば一瞬で通じますよね。
どの分野でも専門家同士は専門用語で話します。
医者同士の会話なんて、素人には全然分からない。
でも、それが正しいやり取りなんです。
だからコーチも、用語をどんどん使っていきましょう。
選手に覚えさせること自体が育成につながります。
まとめ
バスケの専門家が持つべき2つの視点。
-
アクションに分解できる
-
専門用語を使える
これがあると、試合の見え方が変わります。
そして指導の言葉が短く、シンプルになり、選手に伝わりやすくなる。
あなたもぜひ、この2つを意識してみてください。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。