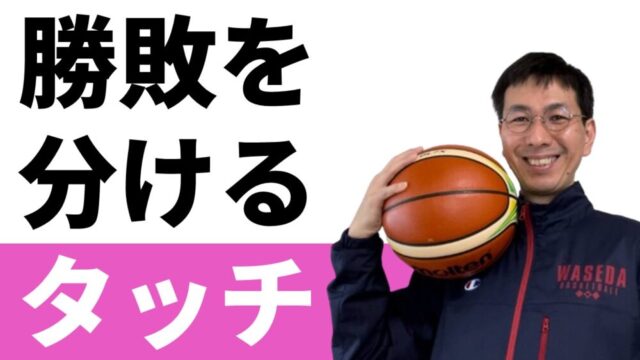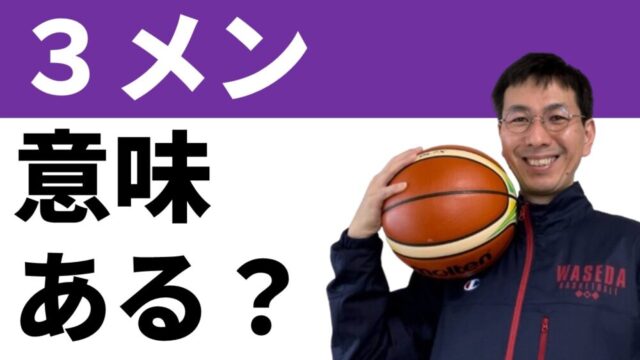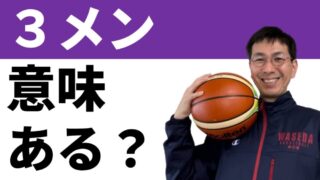練習はコートを狭くすると意味が変わる【バスケの大学】
こんにちは、三原です。
今日も「バスケの大学」をご覧いただき、ありがとうございます。
今回は「コートの広さによって練習の意味は変わるんですよ」というお話です。
きっかけは、YouTubeのコメント欄にいただいたご質問でした。
「1対2のドリブル練習、どのくらいの広さでやるのがいいですか?」
この質問、とても良い問いだと思ったので、ブログで深掘りしてお話ししてみますね。
広くすればオフェンスがやりやすくなる
まず基本の話からいきましょう。
コートが「広ければ広いほど」、オフェンスはやりやすくなります。
そして「狭ければ狭いほど」、ディフェンスがやりやすくなる。これは原則です。
例えば、オールコート1対1の練習を想像してください。
オフェンスは自由に逃げられますよね。ドリブルしてどこにでも行ける。ディフェンスはそれを追いかけ続けなきゃいけない。とてもきつい練習になります。
でもこれを、ハーフコートの半分、さらに1/4とどんどん狭くしていくと、どうなるか?
今度はオフェンスが苦しくなって、ディフェンスは楽になるんです。ダブルチームで挟みやすくなるし、逃げ道が少なくなるから。
つまり、同じ1対2の練習でも、「広さを変えるだけで目的が変わる」んです。
-
オフェンスで「ドリブルに自信を持たせたい」なら、広めに設定する。
-
ディフェンスで「挟む・奪う成功体験をさせたい」なら、狭く設定する。
練習の目的に応じて、広さを変える。この発想が、指導者には必要なんです。
あえて“きつくする”ことで成長する
もうひとつ、トレーニングの原則で「過負荷の原則(オーバーロード)」という考え方があります。
これは「実際の試合よりも、ちょっと厳しい条件で練習することで効果が上がるよ」というものです。
たとえば、ドリブルのボールキープを練習するとき、あえて狭いエリアにしてみる。
ピボットやスクリーンを教えるとき、動けない中でやらせてみる。
そうすると、選手は「技術」で勝負するしかなくなるわけです。
逆に、ディフェンスを鍛えたいなら、あえて広いコートで守らせてみる。
フットワーク、反応、カバーリング…すべてが必要になります。
これは、上級者にとても有効です。
同じ練習でも、「ちょっと難しくしてやる」ことで、技術も判断力も、ぐんと伸びる。
ちなみにうちのチームでは、5~6年生や中学生に対しては、積極的にこういった“きつめ設定”を取り入れています。
試合を想定するなら「狭くしてリアルに」
練習の最後の目的として、「試合を想定した実戦的な練習をしたい」という場合もありますよね。
このときに大事なのが、「実際の試合ってそんなに広く使えないよ」という視点です。
試合の1対1って、オールコートじゃありません。
ハーフコートでもありません。
だいたい、フリースローラインの延長線と、制限区域の幅で囲まれた「1区画」ぐらいの広さでプレーしているんです。
これ、審判の世界では「6分割法」といって、コートを6つに区切って見るという考え方があります。
その1マスの中で、実際の1対1、2対2が行われている。
つまり、「本番の広さ」は、実はけっこう狭いんです。
だからこそ、試合を想定して練習したいなら、「あえて狭くして」そのリアルな空間で練習することが大切なんです。
選手に伝えるときも、
「この練習は、実際の試合で起こる狭さなんだよ」
と説明すると、納得してくれます。
そして、より実戦的な判断と技術が身につくようになります。
ちなみに、「体育館が狭い」「コートが使えない」という学校もありますよね。
でもそれ、逆にチャンスです。
「狭い=試合に近い」と考えれば、どんどんその狭さを活かしていきましょう。
おわりに
今日は「コートの広さで練習の意味は変わる」というお話でした。
-
広くすればオフェンスがやりやすくなる
-
狭くすればディフェンスがやりやすくなる
-
上級者には、あえて難しい設定で過負荷をかける
-
試合を想定するなら、狭くして“リアル”にやる
この考え方を持っていれば、体育館の大きさに関係なく、練習の質は上げられます。
「コートの広さを、目的によって意図的に変える」
ぜひ、今日から意識してみてください。
あなたのチームの練習に、少しでも参考になればうれしいです。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。