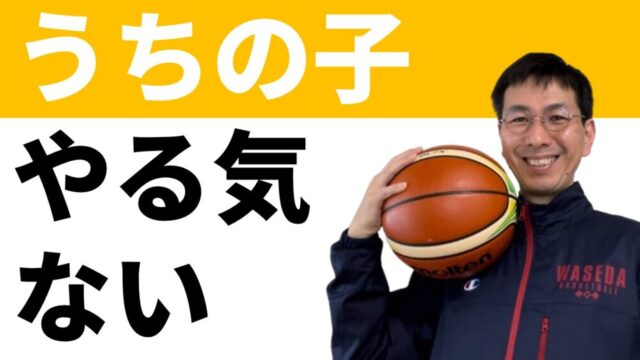1対2の練習がとても大事な理由
こんにちは、三原です。
いつも読んでくださって、ありがとうございます。
今日はちょっと変わった練習の話をさせてください。テーマは「1対2の練習」です。
1対2? なんでそんな不利な練習をするの? って思った方もいると思います。けれど、わたしは「すべてのオフェンスは1対2から始まる」と思っています。
なぜそう言えるのか、今日はその理由と、具体的な練習方法をお話しさせてください。
すべてのオフェンスは「1対2」からはじまる
オフェンスの目的は、もちろんシュートを決めることです。
ただ、シュートチャンスをつくるためには、相手のディフェンスを崩さなければなりません。これがなかなか難しい。でも、だからこそ「1対2の状況を意図的につくる」ことが大事になるんです。
たとえば、オンボールスクリーン。
今や高校生以上のレベルでは当たり前のように使われるこのプレー。スクリーンに行って、ドリブルで使えば、一瞬、オフェンスの選手にディフェンスが2人つく状態、つまり「1対2」が生まれます。
この瞬間、どこかにノーマークができる。あるいはディフェンスが無理なクローズアウトをしなければならなくなる。そこでパスを出せれば、ノーマークでシュートが打てるし、クローズアウトを利用してドライブもできる。
また、スイッチディフェンスが起きれば、そこにミスマッチが生まれる。たとえば、小さいガードが大きなセンターを守らなきゃいけないような状況。これも攻めどころですよね。
オフェンスは、
1対2をつくる → クローズアウトを攻める
または、
1対2をつくる → ミスマッチを攻める
このどちらかしかない、と言っても過言ではないとわたしは思っています。
ボールをなくさないことが最重要
ただ、ここで1つ大きな問題があります。
せっかく1対2の状況をつくれたとしても、ボールを失ってしまったら意味がない。
2人に囲まれて焦ってしまい、無理なパスを出してターンオーバー。あるいはドリブル中に弾かれて速攻される。こういうシーン、試合中によくありますよね。
この「1対2の瞬間に、ボールを失わない力」こそが、オフェンスにおいて非常に重要なんです。
ところが、こういう状況に慣れていないと、心理的に怖くなってしまいます。
「また取られるかもしれない」
「この前もミスしちゃったし…」
こういう不安がプレーに影響を与えてしまいます。
だからこそ、練習で「1対2になってもボールを失わない」ことを経験しておく必要があるんです。
わたしが言いたいのは、1対2で囲まれた瞬間こそ、オフェンスの起点なんだ、ということ。
「お、今、自分が相手を2人引きつけたな」
「じゃあ、ここからチャンスが広がるぞ!」
こう考えられるようになった選手は、強いです。
シンプルな練習で、強い選手を育てる
じゃあ、どうやってこの「1対2の瞬間にボールを失わない力」を鍛えるか。
答えはシンプルです。1対2の練習をすればいい。
わたしがオススメするのは、以下の2つです。
ドリブルで逃げ切る「1対2」
1人の選手がドリブルをついて、2人のディフェンスが追いかける。
30秒間、ドリブルだけで逃げ切ることを目標にします。これが意外とキツい。でも、子どもたちはゲーム感覚で楽しめます。
この練習は、あの能代工業の伝説の練習にもありました。田臥勇太選手がいた時代の話です。
ディフェンス2人がついてくる状況で、空間の使い方、視野の確保、姿勢の低さ、そして冷静な判断。すべてが求められます。
ピボットだけで逃げる「1対2」
もうひとつは、ドリブル禁止の1対2。
ピボットとパスフェイク、ボールハンドリングだけで、2人に囲まれた状態を10秒耐える。
こちらはドリブルに逃げられない分、より“怖さ”を感じます。
けれど、この練習を通じて、ボールを守る力がぐんと伸びます。身体の向き、姿勢の低さ、そして足の運び方。そういったファンダメンタルが身につくんです。
まとめ:囲まれても動じない選手をつくろう
ということで今日は、「1対2の練習をしよう」というテーマでお話ししました。
1対2を避けるんじゃなくて、
1対2になってもボールを守れる選手を育てる。
それができれば、オフェンスはもっと自由になりますし、戦術の幅も広がります。
「囲まれても怖くない」
「むしろ、チャンスが広がっている」
そう思える選手を1人でも育てられたら、チームは確実に強くなります。
ぜひ、今日の練習から1対2を取り入れてみてください。
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。