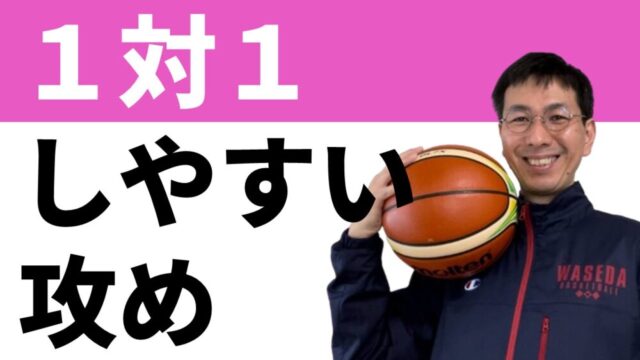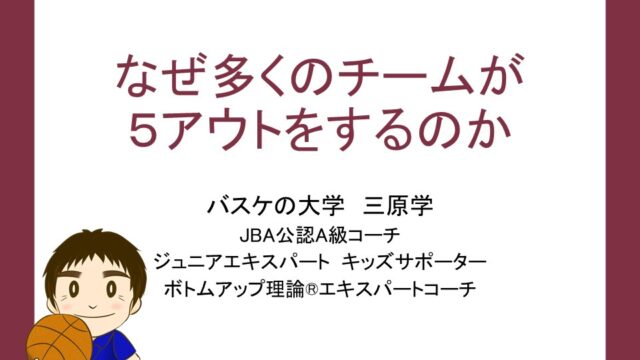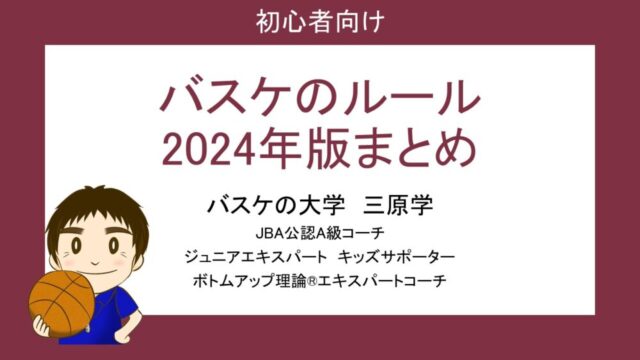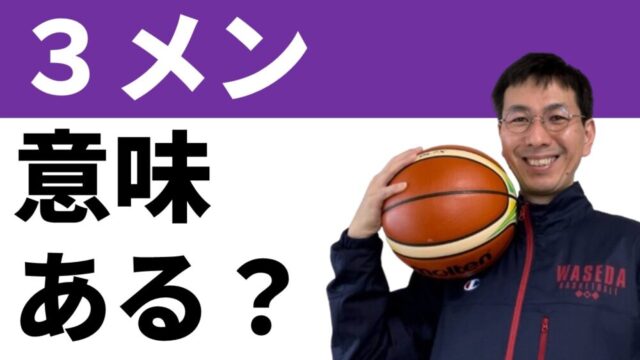リバウンドは「床」!ボックスアウトの極意
こんにちは、三原です。いつもお読みいただき、ありがとうございます。
今日は「リバウンド」についてのお話です。テーマはずばり、ボックスアウトのコツです。
先日、メルマガ読者の方からこんな質問をいただきました。
中学生男子チームを指導しています。背が高い選手が少なく、リバウンドで負けてしまうことが多いです。どんな練習や声かけが必要でしょうか?
ということで、今日はこの質問に答える形で書いていきます。
リバウンドは「高さ」じゃなく「床」
私が好きな合言葉があります。それは「リバウンドは床」。
これは3×3のコーチから教わった言葉なのですが、実に本質を突いています。
リバウンドというと「ジャンプの高さがものを言う」というイメージがありますよね。
でも、私の経験上、高さで取られるのは半分くらいです。残り半分は、肩より下の高さでの競り合い、つまりポジション争いで負けているんです。
ボールに目を奪われ、マークにつかれてしまい、結局押し込まれて取られる。そんな場面をよく見かけます。
だからこそ、リバウンドは床=平面のポジション取りが重要なんですね。
シューターにはリバースターン、オフボールにはフロントターン
では、どうやってボックスアウトするのか。今日はフットワークのコツを2つお伝えします。
1つ目はシューターにはリバースターンです。
シュートチェックで前に出した足を軸に、後ろ回りでボックスアウトします。これが正しいフットワークです。
2つ目はオフボールにはフロントターンです。
ボールを持っていない相手に対しては、自分から前にぶつかりに行くイメージ。ヒットファーストと言われるように、こちらから当たる。そのためにはフロントターンでしっかり正対します。
シュートが打たれた後に、みんななんとなく体を回しているチームが多いですが、この2つを意識するだけで大きく変わります。
特にオフボールは4人もいます。4人がフロントターンでしっかり抑えれば、リバウンドのチャンスはぐっと高まります。
ディフェンスと同じく「ノーミドル」
リバウンドの時も、ディフェンスの原則を活かしましょう。それが「ノーミドル」です。
オフェンスリバウンドに入られる時、中央(ミドル)方向に入られると、簡単に取られたり、取られた後に速攻を食らったりします。
逆に、ベースライン方向に追い出していけば、もし相手に取られてもそのままディフェンスポジションに戻りやすいんですね。
リバウンドもディフェンスの一部だと考え、絶対にミドルは取らせない。この意識が大切です。
リバウンドは「床」と「習慣」
練習の中でリバウンドを習慣化することもポイントです。
1対1でも、2対2でも、シューティングドリルでも、最後は必ず「リバウンドで終わる」。
これを徹底しましょう。
今の子どもたちはSNSでバスケのハイライトをよく見ます。
SNSでは3ポイントや華麗なアシストばかりが取り上げられ、リバウンドが褒められることはまずありません。
だからこそ、指導者がリバウンドを褒めてあげることが必要です。
良いリバウンドをした時に「ナイスリバウンド!」と声をかけるだけで、選手は「これが大事なんだ」と分かるようになります。
まとめ
今日のお話をまとめます。
-
リバウンドは床=ポジション取りが大事
-
シューターにはリバースターン、オフボールにはフロントターン
-
ノーミドルで守る
-
すべての練習でリバウンドを強調する
-
SNSでは褒められないから、コーチが褒める
これを意識していけば、背が低いチームでもリバウンドは必ず伸びます。
そしてリバウンドが取れれば、試合はぐっと有利になります。
ぜひ、明日の練習から実践してみてください!
今日の参考文献
最後にお知らせ
ありがとうございました。
バスケの大学では、指導者の悩み解決になるお話を無料メルマガで発信しています。
最初の1通目でプレゼント動画もありますので、ぜひこれを機にメルマガの登録をよろしくお願いします。
YouTube「バスケの大学」では、ラジオだけでは伝わらない図などを使った戦術解説をしています。
週に1~2本の放送をアップしているので、ぜひこちらもチェックしてください。
最後に、バスケの大学「研究室」では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。
- ここでしか書けない話を共有したり
- メンバーさん全員の質問に真剣に答えたり
- 月に1回のオンライン勉強をやったり
しています。もし興味のある方は案内ページを一度のぞいてみてください。

最後までブログをお読みくださり、感謝しています。
ありがとうございます。
三原学でした。それでは、また。
追記
アマゾンの電子書籍(kindle)で本をたくさん出しています。
ちなみに、アマゾンアンリミテッドの方はすべて無料で読めます。
あと、アマゾンといえば、耳で聞くオーディブルもおすすめです。
無料キャンペーン中にダウンロードした本は、ずっと聞き続けられるので、お試しすることをおすすめします
記事を最後までお読みくださり、感謝しています!
このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。
そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。
同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。
最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。